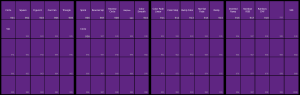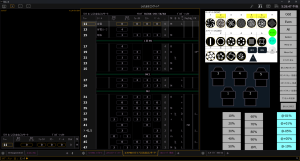~光の“性質”が、舞台の“目的”をかなえていく~
舞台照明の仕事を語るときに、よく出てくるキーワードがあります。
それが――
「光の性質(Quality)」と「照明の目的(Function)」。
ちょっと難しく聞こえるかもしれませんが、これは実はとてもシンプルで本質的な考え方なんです。
◉ 光の“性質”とは?
照明における光は、次の4つの“性質”を持っています。
| 光の性質 | 何を意味する? |
|---|---|
| Intensity(明るさ) | 光の強さ。どれくらい明るいか、まぶしいか。 |
| Color(色) | 光の色味。赤、青、黄色など感情や時間を伝える色。 |
| Distribution(分布) | 光の方向や広がり方。どこから、どんな角度で当たるか。 |
| Movement(動き) | 光がどう変化するか。点灯・フェード・動きなど。 |
これらは照明デザイナーがコントロールできる「道具」です。
でも、ただコントロールするだけじゃ意味がないんです。
◉ 照明の“役割”とは?
照明には、「こういうことを達成したい!」という目的があります。
代表的なものを5つ紹介します。
| 照明の目的 | 簡単にいうと… |
|---|---|
| 視認性(Visibility) | ちゃんと見えること。役者の顔や動きをはっきり見せる。 |
| 形の表現(Form) | 人や物の立体感を出す。平面じゃなく“奥行き”を感じさせる。 |
| 構図(Composition) | 舞台全体のバランスをとって、美しく見せる。 |
| ムード(Mood) | 感情や雰囲気をつくる。喜び・悲しみ・緊張などを照明で演出。 |
| 情報の伝達(Information) | 場所や時間などを、光でさりげなく伝える。 |
◉ 「性質」で「目的」を達成する!
ここが一番大事なポイントです。
舞台照明では、「光の性質」をうまく使うことで、「照明の目的(役割)」を実現していくのです。
たとえば…
▶ 明るさ(Intensity)を調整して【視認性】を達成!
観客がちゃんと演者を見られるように、強い光で顔を照らします。
逆に、注目してほしくない背景は暗くして、自然に“視線を誘導”します。
▶ 色(Color)を使って【ムード】を演出!
暖かいオレンジの光 → 幸せ・安心
冷たい青い光 → 不安・悲しみ
…というように、色には“感情を揺さぶる力”があります。シーンの空気を伝えるのにぴったりです。
▶ 分布(Distribution)で【形の表現】をつくる!
真正面からの光だけだと、顔が平面的に見えてしまいます。
斜め上からの光を使えば、頬に影ができて、立体感が出てくる。
この“光と影のバランス”が、人を自然に、魅力的に見せるんです。
▶ 動き(Movement)で【情報】を伝える!
ゆっくり暗くなっていく → 夜になったことを表現
スポットが急に動く → 注目ポイントが変わったことを示す
動きのある照明は、演出の“語り部”として重要な役割を果たします。
◉ 光の性質を“目的”にリンクさせるのが、照明デザイン!
照明デザイナーの仕事は、ただ光を当てることではありません。
「なぜこの光にしたのか?」「どんな効果を狙ったのか?」
――それを考えて、光の性質を、照明の役割に結びつけるのがプロの照明です。
それは、まるで「光で物語を語る」仕事。
もし、あなたが舞台や照明に少しでも興味があるなら、この“性質と役割の関係”を知っておくだけで、照明の見え方がガラッと変わるはずです。
◉ 最後に:照明は“3Dの塗り絵”を完成させる最後の一筆
舞台照明は、「もう一人の登場人物」とも言われることがあります。
でも、私を教えた教授は照明をこう捉えていました――照明とは、舞台という立体空間に色や質感、空気感を与える“3Dの塗り絵”のようなものだと。
役者の演技、舞台美術、衣装――それぞれが、舞台の「輪郭」や「枠線」を描いていきます。
そして最後に、照明がその空間に光を差し込むことで、舞台の絵は完成します。
照明があることで、風が吹くように感じたり、時間の流れや感情の揺れが伝わったり。
光があるからこそ、舞台は生きた世界になるのです。
舞台照明は、技術であり、アートであり、そして“感情を動かす力”にもなります。
これから照明を学ぶみなさんにとって、この「性質と役割」のつながりが、第一歩のヒントになりますように。